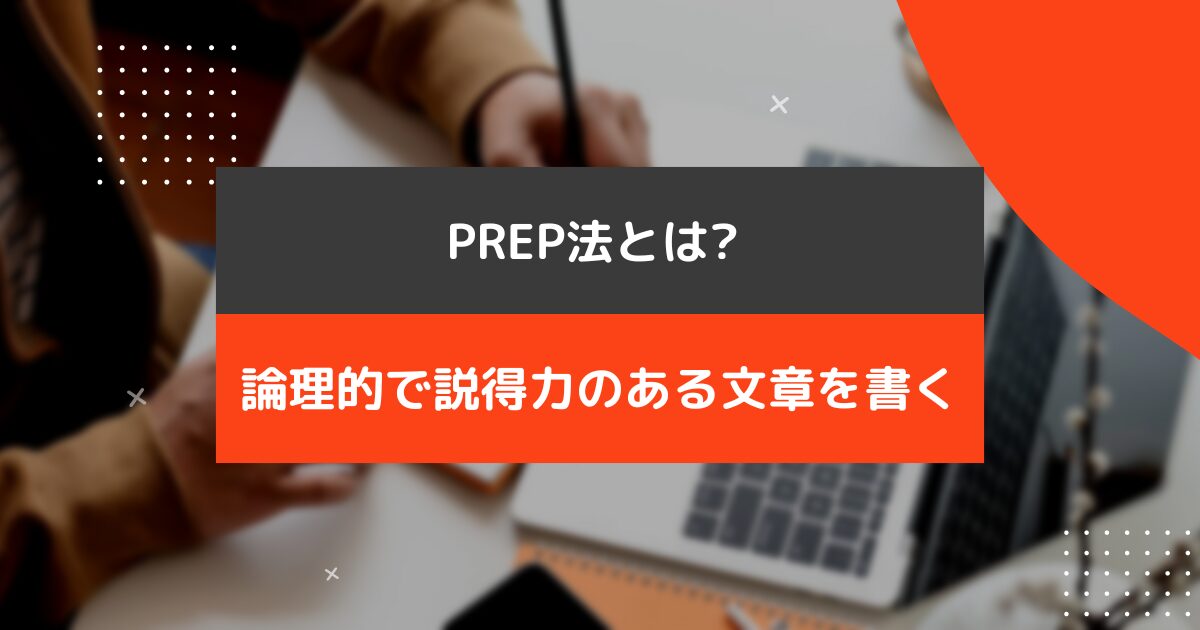そう思う方もいるかもしれません。
PREP法を使えば、結論から話すことで相手に内容が伝わりやすくなり、説得力のある表現が可能になります。
この記事では、PREP法の基本構成、テンプレートの活用方法、ビジネスや面接での実践例、さらには間違いやすい使い方まで、幅広く解説していきます。
PREP法とは?ビジネスで必須の伝わる話し方・書き方の基本
人前で話すときや文章を書くとき、伝えたいことがうまく相手に届かない。
そんな経験はありませんか?
特にプレゼンや提案、自己PRなど、「相手に納得してもらう」ことが重要な場面では、話し方や構成が結果を大きく左右します。
そこで活用したいのが、「PREP法」です。
このフレームワークは、論理的で説得力のある伝え方を可能にします。
はじめに、このPREP法の基本構成から見ていきましょう。
PREP法の構成とは?4つの要素を簡単に理解する
PREP法とは、
Point(結論)
Reason(理由)
Example(具体例)
Point(再結論)」
の流れで話を組み立てる手法です。
相手が知りたいことを最初に提示し、理由と具体的な裏付けを示したうえで、最後にもう一度要点を強調するため、聞き手や読み手にとって非常にわかりやすい構造になります。
では、4つの要素を順番に見ていきましょう。
Point(結論)
最初に提示するのは「結論」です。
相手がもっとも知りたい情報を冒頭で伝えることにより、話の全体像がつかみやすくなります。
たとえば、「PREP法を使えば、伝え方に説得力が生まれます。」といった一文がそれにあたります。
Reason(理由)
次に、その結論を支える理由を述べます。
ここでは、「なぜそう言えるのか?」という根拠を明確にすることで、論理の一貫性が高まり、納得感を与えることができます。
Example(具体例)
続いて、具体例を提示します。
「PREP法を使ったら、面接で『わかりやすい』と好印象を得られた」など、実体験やシミュレーションを挙げることで、読者は自分の状況と重ね合わせやすくなります。
Point(まとめ)
最後にもう一度、結論を述べて話を締めくくります。
同じ内容でも、最後に再確認することで印象に残りやすくなるのがPREP法の特徴です。
このように、PREP法は相手に「伝わる」話し方を実現するための基本型なのです。
PREP法が選ばれる理由とビジネスでの重要性
ここまででPREP法の構造は理解できました。
では、なぜ多くのビジネスパーソンがこの手法を実践しているのでしょうか?
その理由は、「論理性」と「スピード感」です。
結論から話すため、聞き手は最初から内容の焦点がわかります。
その後の説明も「理由 → 例 → 締め」と進むため、情報の流れがスムーズなのです。
また、社内報告・プレゼン・メール・資料作成など、あらゆるシーンで応用可能です。
つまり、PREP法を身につければ、発信力そのものが格段に上がるというわけです。
SDS法やDESC法との違いとは?PREP法との使い分け方
PREP法とよく比較される構成法に、「SDS法」「DESC法」があります。
それぞれの特性を簡単に見てみましょう。
SDS法は
Summary(要約)
Details(詳細)
Summary(再要約)」
の流れです。
ニュース記事やレポートでよく使われ、要点を端的に伝えるのに適しています。
一方、DESC法は
Describe(描写)
Express(感情)
Specify(提案)
Consequence(結果)」
の順番で進みます。
これは主にクレームや交渉、フィードバックなどの場面で使われる対人関係に特化した方法です。
PREP法は、これらと比べて「説得力」に強いのが特徴です。
論理的かつ共感性のある伝え方が求められるシーンでは、PREP法が最も適していると言えるでしょう。
PREP法の使い方と活用ステップをマスターしよう
PREP法の構成と効果がわかったところで、次は「実際にどう使うのか?」という段階に進みましょう。
ここでは、PREP法の基本的な使い方と活用できる場面、そして日常業務や面接での応用方法について紹介します。
PREP法を使う場面と流れの全体像
PREP法は、実にさまざまなシーンで使われています。
社内会議での報告や資料説明、プレゼンテーション、営業トーク、さらにはSNS投稿やブログ記事に至るまで、使い道は多岐にわたります。
使う流れとしては、まず話すテーマや伝えたい主張をひとつに絞ります。
そのうえで、結論 → 理由 → 具体例 → 結論(まとめ)の順に内容を組み立てます。
ポイントは、最初に何を伝えたいのかを明確にすることです。
この部分が曖昧だと、PREPのフレームに当てはめても伝わりません。
PREP法は単なる構成ではなく、「意図を整理し、伝える力を鍛えるツール」なのです。
PREP法のテンプレートで型を身につける
PREP法を習得する近道は、型を繰り返し使うことです。
ここでは、具体的なテンプレートを紹介しながら、自然とPREPが使えるようになるコツをお伝えします。
プレゼン用テンプレート
プレゼンでは、主張や提案を端的に伝える力が求められます。
以下の型が役立ちます。
「私の提案は〇〇です。なぜなら、〇〇という理由があります。実際に、〇〇という事例もあります。ですから、〇〇すべきです。」
この流れを意識するだけで、話がスッキリまとまり、聞き手にも好印象を与えることができます。
メールやチャット用テンプレート
文章でもPREP法は強力です。
たとえばビジネスメールで何かを提案する場面では、以下のような構成になります。
結論:〇〇をご提案します。
理由:〇〇という背景があるためです。
例:たとえば、〇〇のようなケースがあります。
結論:以上より、〇〇が最適だと考えます。
文字だけのやり取りでは構成力が物を言います。
PREPを使えば、短くても伝わるメールが書けるようになります。
SNS・ブログ投稿用テンプレート
SNSやブログでもPREP法は応用できます。
たとえば、読者に役立つ情報を届けたいときは、次のような流れで書くと効果的です。
〇〇は絶対にやるべきです。なぜなら、〇〇な理由があるからです。
たとえば、私は〇〇を実践して、△△という成果が出ました。
だからこそ、〇〇をオススメします。
このように、PREP法を意識するだけで情報発信の説得力が高まります。
PREP法を面接・自己PR・志望動機で使う方法
PREP法はビジネスだけでなく、就職・転職活動でも非常に効果を発揮します。
特に「自己PR」や「志望動機」を話す場面では、伝え方の良し悪しが印象を大きく左右します。
PREP法を用いれば、結論を先に述べることで面接官の興味を引き、その後の説明で納得感を持たせることが可能になります。
面接での自己紹介の例
たとえば、次のような流れが有効です。
私は〇〇が得意です。なぜなら、〇〇という経験があるからです。
実際、前職では〇〇を担当し、△△の成果を出しました。
ですから、新しい職場でもこの強みを活かせます。
このようにPREP法を用いると、自己紹介の内容にブレがなくなり、面接官の記憶にも残りやすくなります。
志望動機にPREPを活かす例
貴社を志望する理由は、〇〇を実現できると考えたからです。
私は〇〇という経験があり、その中で△△を大切にしてきました。
貴社の〇〇という理念と強く共感し、自分の価値観と一致すると感じています。
だからこそ、ぜひ貢献したいと思っています。
PREP法を使えば、単なる志望理由ではなく、“伝わる”志望動機に昇華させることが可能です。
自己PRで説得力を出すコツ
自己PRは、PREP法の真価が問われる場面です。
曖昧なエピソードや抽象的な表現ではなく、「結論 → 理由 → 具体例 → 結論」を貫くことで、説得力が一段と増します。
PREP法を使いこなせるかどうかが、他の応募者と差をつける鍵になります。
PREP法の例文を通して実践的に理解しよう
PREP法の構造や使い方がわかっても、実際に自分で使えるかどうかは別の話です。
そこで重要になるのが、「例文を通じて型を身につけること」です。
このセクションでは、ビジネスシーンや自己PRなどで使える具体的な例文を紹介します。
「PREPってこう使えばいいのか」と、実感してもらえるはずです。
ビジネス会話・報告での例文
ビジネスの場では、上司への報告や同僚への説明など、限られた時間で的確に伝える必要があります。
PREP法を用いることで、話の焦点が明確になり、相手の理解度も格段に上がります。
社内報告での使い方
例)
本日のミーティングは午後ではなく午前に実施すべきです。
なぜなら、午後は営業部全体が外出してしまうため、参加率が低下する可能性があるからです。
実際に先月の午後開催では出席率が50%を下回りました。
以上から、午前中の実施が最適だと判断します。
このように結論を先に出すことで、話の流れがスムーズになります。
上司もすぐに判断しやすくなるのです。
クライアント対応での使い方
例)
今回のキャンペーンではWeb広告よりSNS広告を採用すべきです。
理由は、御社の商品はターゲットが20〜30代女性であり、SNSでの反応率が高いためです。
実際、同業他社の事例ではSNS経由のCV率が1.8倍に上がったというデータがあります。
したがって、SNS広告の導入を推奨いたします。
このようにPREP法を使えば、論理と実績を組み合わせた提案ができます。
結果として、クライアントの納得度も高くなります。
面接や自己PRのPREP法例文
PREP法は就活や転職活動の武器にもなります。
とくに自己PRの場面では、「伝える順序」が評価を左右します。
以下のように、フレームを意識して組み立てると説得力がグッと増します。
例)
「私の強みは課題解決力です。
大学時代に所属していたゼミで、発表内容に対するフィードバックが厳しかったことがきっかけでした。
私は全体構成を見直し、伝え方を変えた結果、ゼミ内で高評価を得られるようになりました。
この経験から、状況に応じた改善と工夫ができる柔軟性を身につけました。」
このような形でPREPを取り入れると、曖昧な自己PRから脱却できます。
評価されやすい文章になるのです。
好きなものをテーマにしたカジュアルな例文
PREP法はカジュアルな会話や日常の発信にも応用可能です。
「好きなもの」や「おすすめ」を語る場面でも、PREPを意識すると伝わりやすくなります。
例)
「私は味噌ラーメンが一番好きです。
理由は、コクが深くてスープと麺の相性が抜群だからです。
たとえば、札幌の〇〇というお店では、濃厚だけど後味すっきりの味噌ラーメンが食べられます。
だからこそ、ラーメンといえば味噌だと思います。」
このように、話す内容がどんなにカジュアルでも、PREP法を使えば説得力が増すのです。
PREP法の練習と応用のポイント
PREP法を理解し、例文を参考にしても、いざ自分の言葉で使おうとすると「うまく言えない」と感じる方も多いです。
ここからは、PREP法を実際に使えるようになるための練習方法と、より説得力を高める応用のコツを解説します。
PREP法を上達させるための練習法
PREP法は、ただ読んで理解しただけでは身につきません。
繰り返し練習することで、自然と「伝わる話し方」ができるようになります。
1日5分でできる構成練習
まずは、身近な話題をPREP法で組み立ててみましょう。
たとえば「朝食にはご飯がいい」「雨の日は読書が最適」といったテーマでも構いません。
1日1テーマだけでも、結論・理由・具体例・結論の流れで文章を考えてみることで、PREPの型が自然に身についてきます。
慣れてきたら、頭の中で話す練習もおすすめです。
会話の中でもPREPを使えるようになれば、思考と発信が一致するようになります。
音読トレーニングの活用法
文章を「声に出して読む」という練習も効果的です。
特に、自分で作ったPREP文を声に出して確認すると、わかりにくい部分や冗長な表現に気づくことができます。
録音して聞き直すことで、話のテンポや説得力もチェックできます。
音読と振り返りを繰り返すことで、「伝える力」が段階的に強化されていきます。
PREP法の悪い例・失敗例を知っておこう
PREP法はシンプルな構成ですが、使い方を間違えると逆効果になることもあります。
ここでは、よくある悪い例とその修正方法を紹介します。
よくあるNG構成と改善例
悪い例)
「私は〇〇だと思います。理由は色々あります。たとえば、△△などです。ですので、よろしくお願いします。」
このように抽象的すぎる表現は、PREP法の良さを打ち消してしまいます。
「何を言いたいのか」が曖昧なままでは、説得力がありません。
改善例)
「私は〇〇に自信があります。なぜなら、△△という経験があるからです。具体的には、〇〇というプロジェクトで成果を出しました。だからこそ、今後も活かせると考えています。」
PREP法を使うときは、必ず具体性・根拠・一貫性を意識しましょう。
PREP法のメリットとデメリット
PREP法の最大のメリットは、結論から話すことで主張が明確になる点です。
ビジネスでは時間も限られているため、端的に要点を伝えられるPREPは非常に重宝されます。
また、理由と具体例で補強するため、聞き手の納得を得やすいという強みもあります。
一方で、構成がパターン化してしまうと、**「機械的に聞こえる」**というデメリットもあります。
そのため、相手や場面に応じてトーンを変えたり、言い回しを工夫したりする柔軟性が大切です。
PREP法は万能ではありませんが、ベースとして身につけておけば、どんな場面でも応用が利く「伝える力」の土台になります。
まとめ
PREP法は、伝えたいことを端的かつ論理的に届けるための強力なフレームワークです。
「結論→理由→具体例→結論」の型を使えば、話し方も書き方も格段に伝わりやすくなります。
プレゼンや面接、文章作成にすぐ活用してみましょう。